エンジニア成長のカギは基礎力──本気で育成するために導入したRecursion
そう語るのは、株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ代表取締役の近藤慎哉氏。同社では、将来的に現場で長く活躍できるエンジニアを育成するため、法人研修にRecursionを導入。足腰が強く伸びるエンジニアを育てる同社の取り組みについて詳しく話を伺いました。

株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ様
会社紹介
会社の具体的な事業内容について
当社、株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズは、2022年の2月に創業し現在4年目に入ったところです。
当社が所属するヘッドウォータースグループでは主に先端技術を提供しており、親会社を中心に「クロステックAIソリューション事業」を展開しています。その中で弊社は、「人材の採用・育成・供給」を主な役割として担っています。
「エンジニアのハタラクを良くする」というビジョンのもと、様々な取り組みを行っていますが、その中でも特に「育成」に力を入れており、その一環としてRecursionを活用しています。
また、グループ全体で「クロステック・ハンズオンワーク」という取り組みも行っており、価値あるエンジニアを育て、クライアント先に能動的に動ける人材としてアサインし、プロジェクトの成功を支援するのが私どもの強みです。
エンジニア育成の課題とRecursion導入の背景
どういった課題やニーズがあったのか
親会社であるヘッドウォータースは2005年に設立され、20年近くにわたりエンジニアを採用してきました。しかし、上場を機にエンジニアのレイヤーが次第に高くなり、採用が非常に難しくなってきたという背景があります。
さらに、多くの方がご存じの通り、現在はエンジニアの採用自体が非常に難しい時代に突入しており、各業種・業態において、優秀な人材の獲得が年々厳しくなっています。こうしたレッドオーシャンの中で、ヘッドウォータースとして採用・育成を進めていくには、まず間口を広げる必要がありました。
弊社が得意とする「ソリューションラインナップを提供できる経験者」の採用とは別に、ヘッドウォータースの文化や文脈をしっかり受け継いでもらえる新しいエンジニアを採用・育成していくことも重要なテーマとなっていました。
こうした背景から、ヘッドウォータースプロフェッショナルズは誕生しました。創業期には、比較的若手層・ポテンシャル層の採用に注力していました。
そのため、「いかにして研修カリキュラムを充実させるか」が、事業成長のカギとなっていました。
とはいえ、当時は社内に若手ポテンシャル層向けの研修カリキュラムが整備されておらず、その構築が大きな課題でした。外部の研修機関に頼ることもありましたが、思うような成果は得られず、課題感が残る結果となっていたのが実情です。
Recursion導入プロセスと活用方法
外部研修と比べてRecursionは何が違ったのか
まず前提として、すべてがRecursionだけで完結しているわけではありません。ただ、長年にわたりヘッドウォータースグループでエンジニア育成に携わる中で強く感じていたのは、「基礎力が高く、足腰の強いエンジニアほどスキルの伸びが早く、学習コストも低い」ということでした。
これは、単に開発言語を中心に学ぶのではなく、ソフトウェア開発の根本的な仕組みを理解し、その制約条件の中で技術を柔軟に活用できる人こそ、大きな成長を遂げている――という実感に基づくものです。
従来の外部研修では、たとえば「PHPのプロジェクトで活躍できる人材」や「Javaの案件に参画できる人材」を育成することはできましたが、個人としての基礎力や応用力、つまり“個人戦闘能力の高いエンジニア”を育てるという視点では、物足りなさを感じる場面もありました。
こうした課題を踏まえ、研修カリキュラムをゼロから見直す中で、「どのようにして基礎体力を積み上げるか」を重視しながら情報収集を行いました。その結果、Recursionの活用が最も効果的だと判断しました。
開発言語そのものの習得については、別の書籍や動画コンテンツを併用しながら補完する形をとり、育成ラインナップ全体を再構成する方が、我々の状況には適していると考えたのです。
こうして、外部研修の活用を終了し、Recursionを基盤としたカリキュラムへと移行するに至りました。
現在社内でどれくらいのエンジニアがRecursionを使っているか
基本的には、「入社時の研修カリキュラムの一環」としてRecursionを活用しています。
入社のタイミングでRecursionのアカウントを作成し、「コンピュータサイエンス初級」と「中級」のコースを必ず受講してもらう、というのが基本的なカリキュラムの構成です。
この取り組みは2023年1月頃から開始し、現在では、社内エンジニアの約7割がRecursionのコンピュータサイエンス初級・中級コースをしっかりと修了している状況となっています。
なお、入社時点での平均的な経験年数を見ると、当社に入社される方々は、技術系・IT業界、あるいはソフトウェア開発に関わった経験が、おおよそ2.5年から2.8年程度となっています。
経験があるエンジニアでもRecursionで基礎を学ぶ意味があるのか
エンジニアのスキルセットには、明確な線引きができないグラデーションがあると感じています。たとえば「経験年数3年」とひとくくりにしても、その中身には大きなばらつきがあり、実際のスキルレベルには個人差があります。
実際、ある程度の経験がある方であれば、Recursionの「コンピュータサイエンス初級・中級」コースを難なくこなせるケースもあります。しかしその一方で、
- 自分の理解の「解像度の粗さ」に気づく
- フレームワークに頼っていたため、本質的な理解ができていなかった
- 考える力の浅さに気づかされる
といった声も多く寄せられており、受講を通じて「自分には基礎力が足りていなかった」と気づく方も少なくありません。
そうした背景を踏まえると、経験年数にかかわらず、全員に初級・中級コースを受講してもらうことには、十分な意義があると考えています。
Recursion導入後の成果
Recursionを導入したことで、具体的にどのような成果があったのか
まず導入前と比べて、導入後のほうが明らかに成果が出てきていると感じています。特に感じるのは、エンジニアがプロジェクトにアサインされる際のハードルを超えられるようになってきたという点です。
以前は、エンジニアとして現場に入った後に貢献していくためには、
- OJTでなんとか覚えていく
- 現場の先輩に支えてもらいながら、手探りで成長していく
といったケースが非常に多く見られました。
しかし、2023年1月以降は、たとえば経験者の採用が増えてきたという要素もあるかもしれませんが、それ以上にRecursionを取り入れた研修カリキュラムの効果が大きいと感じています。
このカリキュラムを通じて、現場でしっかりと生き残っていけるエンジニアが育っている実感があり、育成の方向性として間違っていなかったと確信しています。
社内展開とモチベーション維持の工夫
最近業務外で学習しているSさんのモチベーション管理や効果的な活用のために、どのような工夫をしているか
まず前提として、入社時の研修については業務時間内で行っていますが、今回は試験的に行っている取り組みであることと、Sさんの状況に合わせて業務外でRecursionに取り組んでもらっています。
この取り組みについては、彼のモチベーションの源泉が「開発業務に関われること」にあるという点が出発点です。現在はDさんと一緒にチームを組んでおり、技術レベルの高いメンバーと共に実務を行うことで、モチベーションの維持につなげています。
一方で、本人の中には「まだ通用していない」という自覚もあり、そのギャップを埋めるためにRecursionを活用しているという状況です。会社としても、その取り組みを積極的に支援しています。
進め方については、基本的に本人の自主性を尊重しており、「毎日2時間学習してください」「日報を提出してください」といったルールは設けていません。あくまで自分のペースで学べるようにしています。
そして、数ヶ月後に成果と進捗を評価する予定です。その際に、もし進捗が芳しくないようであれば「やはりある程度の管理体制が必要だ」と判断し、仕組みを見直す可能性もあります。逆に、順調に進んでいるようであれば、そのやり方をベースにさらなる改善点を一緒に考えていきたいと思っています。
この取り組みが成果を上げれば、他のメンバーへの横展開も視野に入れています。その場合は、テスト的な位置づけではなく、業務時間内に1〜2時間を割り当てるなど、より実用的な形での導入を検討しています。
今回の施策は、過去に成果を出したKさんの学習モデルを再現することも目的とした取り組みです。
Kさんについて入社時のレベル感と現在の担当業務はどのようなものか
Kさんは、入社当初は完全な未経験からのスタートでした。入社後は、Recursionの初級・中級コースを含む研修を受講し、その後、Web開発系のプロジェクトをいくつか経験してきました。
そして、2023年の終盤には生成AI関連のプロジェクトに携わるようになり、以降1年間にわたって、その分野の案件を主に担当してきました。現在では、大手鉄道会社などグループの重要顧客を担当するプロジェクトにもアサインされており、Kさんがいなければ進行が難しい案件も複数あるほどです。
生成AIを活用したシステム開発の領域においては、社内でも高い認知を得ており、技術的な研鑽も欠かさず、日々成長を続けています。
また、エンジニアとしての役割にとどまらず、現在では組織内でリーダー的な立場も担っており、グループ全体を牽引する存在へと成長しています。
このように、未経験からスタートしたKさんは、今では当社の中核を担うキーパーソンとして大きな活躍を見せています。
Recursionへの評価とメッセージ
どのような企業や組織に、Recursionの活用が向いているか
本気でエンジニアを育成したいと考えている企業こそ、Recursionを“登竜門”として活用すべきだと、私は強く感じています。
もちろん、世の中には多種多様な学習コンテンツがあり、質の高い海外教材や、無料で公開されているリソースも数多く存在します。しかし、私たちが実際にRecursionを活用してきた中で特に評価しているのは、学習者が段階的にステップアップできるよう、丁寧に構成されている点です。エンジニアのスキルが確実に一段ずつ引き上げられていく実感が持てる設計になっています。
この「階段の作り方」が非常に秀逸で、他のコンテンツと比べても、学ぶ側にとって無理がなく、かといって甘すぎない——ちょうど良い難易度と構成になっていると感じます。
もちろん、進めていくにつれて難易度は上がり、相応の学習時間も必要になります。しかし、それこそが本気で成長を目指すエンジニアにとっては必要な投資であり、十分に価値のある時間だと考えています。
私自身、「現場で長く活躍し、生き残れるエンジニアをどう育てるか」というテーマを持っています。そのためには、やはり基礎力が不可欠であり、その基礎を確実に身につける環境として、Recursionは非常にフレンドリーで効果的なプラットフォームだと感じています。
本気でエンジニアを目指したい人、そしてエンジニアとして長く活躍し続けたい人にとって、Recursionはその土台を築く最適な場です。
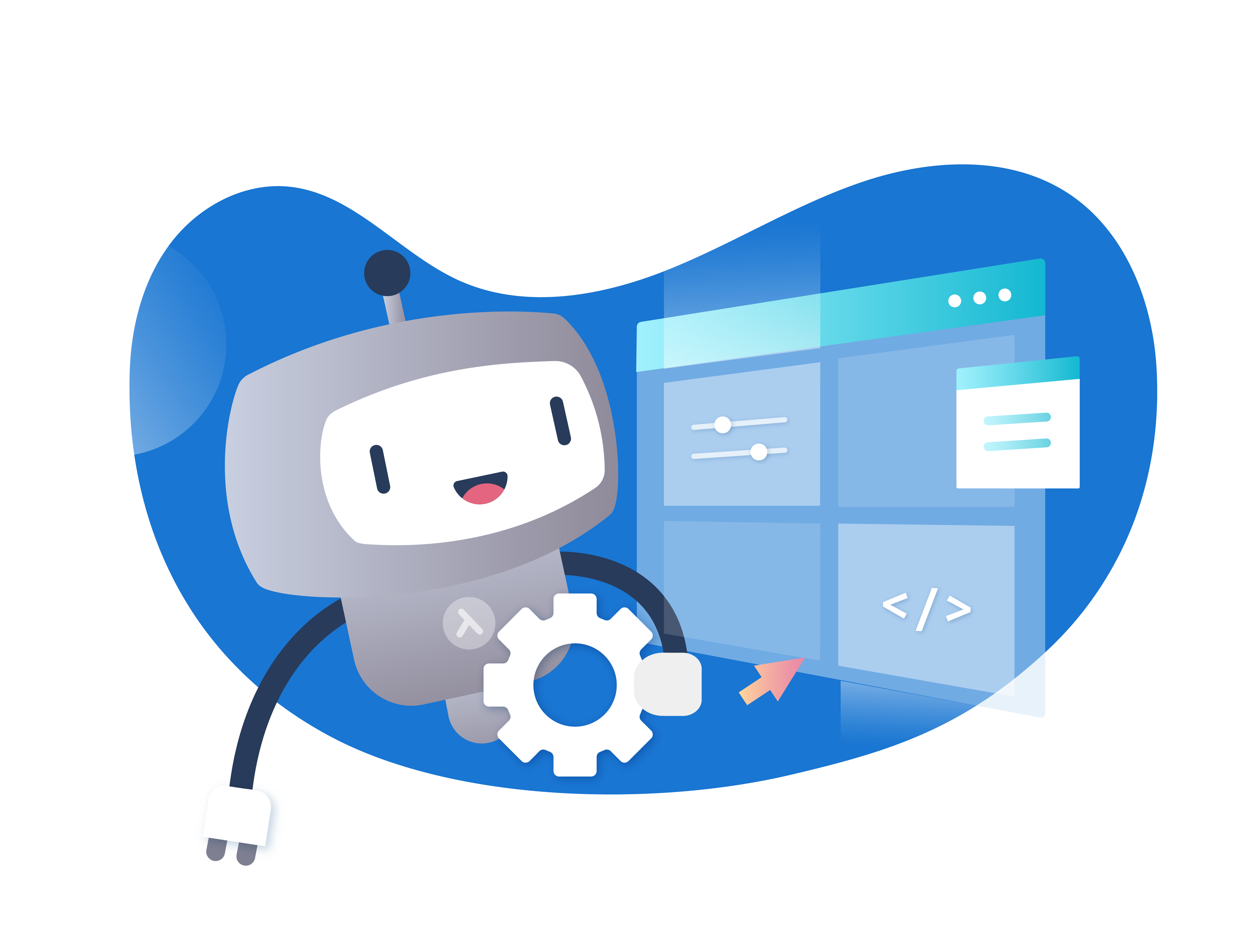
コンピュータサイエンスを学ぶなら
Recursion Business
コンピュータサイエンスの知識をオンラインで手軽に学べるサイトです。人材育成に必要なカリキュラムを揃えています。ご興味のある企業様は無料資料請求を。